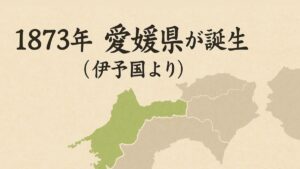【地名のナゾ】「久万高原」「砥部」「伊予」ってどんな意味?
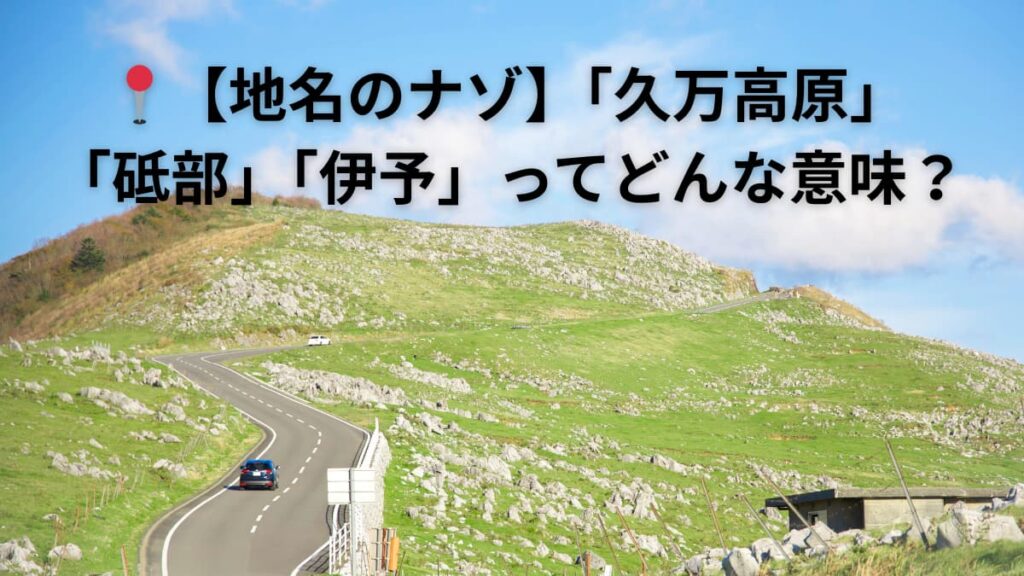
目次
【地名のナゾ】「久万高原」「砥部」「伊予」ってどんな意味?
〜名前に込められた歴史や自然を探ってみよう〜
普段何気なく使っている地名、実はそこには深い歴史や自然との関わりがあるって、ご存じでしたか?
今回は、愛媛県内でも特に気になる3つの地名——「久万高原」「砥部」「伊予」の由来を探ってみました!
🏔 久万高原町(くまこうげんちょう)
「久万(くま)」という地名は、古代の地名「熊野(くまの)」や「高熊山」に由来すると言われています。
「くま」=神聖な山・神のこもる場所という意味があるとも。
また、「高原(こうげん)」は2004年の合併時に加えられた名称で、文字通り四国山地の高原地帯であることを表しています。
🪨 砥部町(とべちょう)
「砥(と)」は砥石(といし)の「砥」で、古くから砥石の産地だったことが由来です。
特に「内子砥」などは全国的にも有名でした。
「部(べ)」は、古代律令時代の行政単位「部民(べみん)」から来ており、砥石づくりに従事していた人々の集まりを意味していたと考えられます。
そして現代では「砥部焼(とべやき)」で全国に知られる町となりましたね✨
🏯 伊予市(いよし)・伊予国(いよのくに)
「伊予(いよ)」は、愛媛県の旧国名。古代の律令制で定められた「伊予国」からきています。
名前の由来は諸説ありますが、古事記に登場する「伊予之二名(いよのふたなのくに)」が起源とも。
「伊予」は神代の時代からの名前とも言われ、最古級の地名の一つです。
🔍 まとめ
- 久万高原:「くま」=神聖な山/高原の自然をあらわす
- 砥部:「砥石の産地+部民」=職人文化のまち
- 伊予: 古事記にも登場する、神代からの地名
💬 最後に…
地名を知ることは、土地のルーツや人々の営みに触れること。
ちょっとした「へぇ〜!」が、愛媛をもっと好きになるきっかけになるかもしれません😊